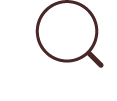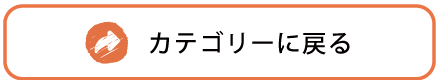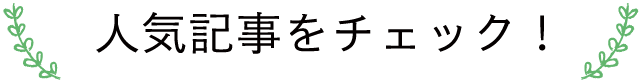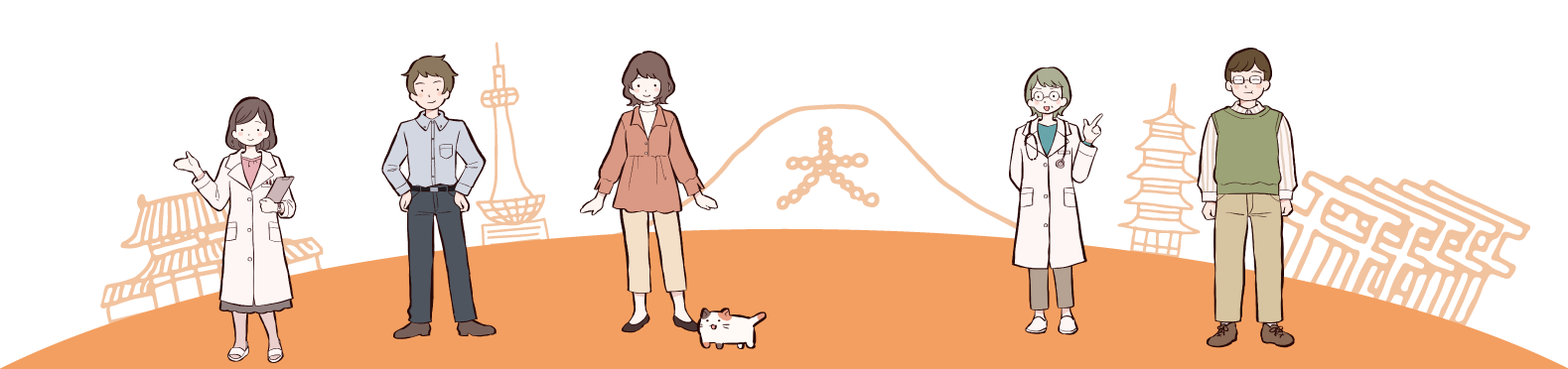日本で昔から食されている小豆は、赤飯や和菓子などで広く親しまれています。
小豆には、糖質の代謝に欠かせないビタミンB1や整腸作用のある食物繊維、むくみの予防になるカリウムやサポニンなどが含まれます。
小豆とは?
小豆の日本での食用の歴史は古く、「古事記」に五穀のひとつとして登場します。昔から人々の生活と密接に関わり、日本や中国、朝鮮では小豆の赤色に魔除けなどの神秘的な力があると信じられ、行事や儀式に用いられていました。
小豆の名の由来は諸説ありますが、江戸時代の学者、貝原益軒の「大和本草」によると、「あ」は「赤色」、「つき」及び「ずき」は「溶ける」の意味があり、赤くて煮ると皮が破れて豆が崩れやすいことから「あずき」になったとされています。
小豆の中でも、特に大粒で煮ても皮が破れにくい特徴を持つものは「大納言」と呼ばれ、あんこの原料や赤飯のほかに、甘納豆や鹿の子などの豆粒の形状を保った製品などにも使われます。
また、小豆と野菜を炊き合わせる料理を「いとこ煮」と呼び、その代表的なものがβ-カロテンを多く含むかぼちゃとの組み合わせです。
小豆の煮方は、乾燥豆を吸水させずにそのまま鍋に入れて水とゆでます。他の豆の場合は吸水させますが、小豆は種皮が硬く十分に戻るまでに時間がかかります。十分に戻っていないと豆粒ごとの吸水状態にばらつきが生じ、煮えむらの原因になることから、家庭では時間をかけて戻すよりも、乾燥豆をそのままゆでることが適しています。
■小豆の選び方
赤色が濃く、ツヤがあってシワがなく、粒がそろっているものを選びましょう。
■小豆の保存方法
湿気を嫌うため、紙袋などに入れて風通しのよい場所で保存しましょう。
食べきれない場合は、ゆでてから冷凍保存しましょう。
小豆の効果
■疲労回復効果
ビタミンB1は疲労回復のビタミンといわれ、糖質の代謝を高めて、疲労物質がたまるのを防ぐ働きがあります。糖質はビタミンB1がないと、スムーズに代謝できず、使われなかった糖質は、疲労のもとである乳酸となって体内に残ってしまうため、ビタミンB1の摂取は疲労回復に役立ちます。
■便秘を改善する効果
小豆に含まれる不溶性食物繊維やサポニンには、腸を刺激して蠕動運動を活発にし、腸内に溜まった不要な老廃物や有害物質を体外へ排出する働きがあるため、便秘の改善が期待できます。
■むくみを予防・改善する効果
ナトリウムの過剰摂取やカリウムの不足などにより、体内の水分バランスが崩れてしまうとむくみにつながることがあります。カリウムを摂ることで、体内の水分バランスが調整され、むくみの予防や改善に働きます。
小豆の皮に多く含まれる苦味成分のサポニンも利尿作用を促すため、むくみ予防に効果的です。
■生活習慣病を予防する効果
食物繊維とサポニンは血中のコレステロール値を下げ、サポニンとカリウムは高血圧を予防するなどの働きがあります。
また、小豆の皮の赤い色素はアントシアニンによるものです。抗酸化作用があるため、生活習慣病の予防が期待できます。

こんな方におすすめ
●疲労を感じている人
●便秘が気になる人
●むくみが気になる人

おさらい
●小豆は乾燥豆の状態で水と一緒にゆでる
●皮に含まれる苦味成分のサポニンはむくみや高血圧、便秘の予防効果が期待できる
●小豆に含まれるビタミンB1は疲労回復に役立つ

・完全図解版 食べ物栄養事典(発行所 株式会社主婦の友社)
・春夏秋冬おいしいクスリ 旬の野菜と魚の栄養事典(発行所 株式会社エクスナレッジ)
・かしこく摂って健康になる くらしに役立つ栄養学(発行所 株式会社ナツメ社)
・公益財団法人日本豆類協会